へき地教育の過酷な現実
1953年12月16日
2021年10月18日
昭和28年12月16日の読売新聞では、全国のへき地教育の過酷な実態を報じている。
- 降水で丸木橋が渡れなくなると荷物用のケーブルで通学する(群馬県中里中)
- 山道が険しいので冬季の通学は部落民が交代で提灯を持っていく(岐阜県)
- 通学路は波が引いたときに数百メートルを命がけで走る(青森県脇野沢村)
- 子供が野球を知らない(北海道厚岸町大黒島小)
- 分校が4つあっても参考書は本校にあるだけ。1つの教室に全学年が集まった時の教え方なんてどこにも書いてない(福島県石城郡川前小)
そして岩手県である。
「日本のチベット」と呼ばれ、小学生と中学生が同じ教室で学んでいるのが24校、炭焼きの季節になると中学生の半分が欠席。
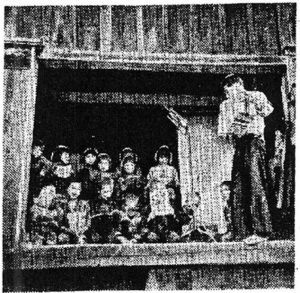
そして、そのような村は親の意識も「子供に敎育はいらない」と学校の必要性を認めず、無医村であり、電燈もないという。
そんなへき地に教員が赴任したいはずもなく、「姥捨て山」「隠居教師」「貧乏くじ教師」などと呼ばれていた。
それで、1年生~6年生が1つの教室で学んでいる「単級小学校」では全国で55%が無資格教師で、25歳以下が43%、勤続年数が5年以上というのは1%もいないという。
正式な教員の資格を取ろうにも、子供たちが置き去りになるので受験に行くこともできず、長崎県の離島では11年も助教という例もあるのだという。
そこで全国教育委員会協議会の北部ブロックが提唱し、へき地教育に関する立法と予算獲得を働き掛けた結果、7月31日に衆議院で、8月6日に参議院で「へき地教育振興に関する決議案」の可決を見たのだという。
