釜石のキリスト教会でゴタゴタ(S35.9.27岩手東海新聞)
1960年9月27日
2025年7月30日
昭和35年9月27日付の『岩手東海新聞』によれば、釜石市大渡町にある日本基督教会・大渡教会で、教会運営をめぐる大きな混乱が生じているという。
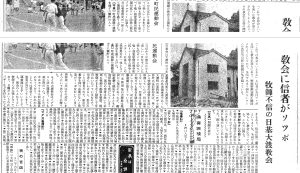 この教会では、かつてはバプテスト派の牧師により、教会員による民主的な運営が行われていた。信者一人ひとりの信仰や意見が尊重される共同体として地域に根づいてきたのである。
この教会では、かつてはバプテスト派の牧師により、教会員による民主的な運営が行われていた。信者一人ひとりの信仰や意見が尊重される共同体として地域に根づいてきたのである。
ところが、近年になって教会の運営方針が変化。新たに派遣された牧師はホーリネス派の影響を受けた人物であり、教会活動のスタイルが一変した。伝道や礼拝を差し置いて、日曜日にバザーを開催するなど、信仰よりも行事が優先されるようになったことに、信者たちは戸惑いと不信感を募らせたという。
実際に、これまで熱心に通っていた日曜学校の子どもたちの姿が見られなくなり、礼拝の出席者も減少。ある信者は「これでは教会ではない」と語り、別の信者は教会を離れる決意を固めた。
記事では「これまでのバプテスト派の民主的な運営から、ホーリネス派の指導者中心の形に変わったことが問題の核心」としている。両派は共にプロテスタントの一系統ではあるが、教会運営や信仰実践のスタイルには大きな違いがある。バプテスト派は個人の聖書理解と会衆の合意を重視するのに対し、ホーリネス派は指導者の霊的権威や「完全聖化」といった熱心な実践主義を特徴とする。
このような変化が、長年の信者にとっては「信仰の場が失われた」と感じさせるには十分だったのだろう。釜石の教会で起きたこの出来事は、地方の信仰共同体において、指導者の姿勢や教派的なスタイルの違いがいかに大きな意味を持つかを物語っている。伝道とは何か、教会とは誰のための場なのか――信仰の原点がいま一度問われているように思われる。